看護師として転職する際に、退職金について下記のような疑問を持っている方も多いでしょう。
「5年働いたら退職金はいくらもらえるんだろう?」
「看護師の退職金相場はいくらなんだろう?」
看護師の退職金は制度や勤続年数で変わるのはもちろん、病院の規模や公立病院か私立病院かによっても異なります。
そこで今回は看護師の退職金について、勤続年数別の相場や計算方法を紹介します。
日赤や済生会の実際の退職金についても解説しているので、これから転職を考えている方は必見の内容です。
看護師の退職金制度は3種類

看護師の退職金制度には、退職一時金制度・企業年金制度・前払い制度の3種類があります。
それぞれどのような制度なのか詳しく解説します。
一般的なのは退職一時金制度
退職一時金制度とは、退職する際に退職金が一括で受け取れる制度です。
一般的に退職金と聞いてイメージするのが、退職一時金制度でしょう。
退職金の金額は病院によって異なり、勤続年数・役職有無・保有資格・職場への貢献度などによって決まります。
また。退職理由が「自己都合」か「職場都合」かによっても退職金額が異なり、職場都合の方が高い金額が設定されていることが多いです。
厚生労働省が平成30年に行った調査によると、医療・福祉業の96,2%が退職一時金制度を導入しています。
参考URL: 平成30年就労条件総合調査
一定の年齢に達したら支給される企業年金制度
企業年金制度とは、一定の年齢に達すると定期的に年金が支払われる制度です。
一生涯支払われる場合と、一定の年齢に達するまで支払われる場合があります。
企業年金制度だけを採用している病院の場合、一定の年齢に達する前に退職すると退職時には退職金が支払われないので注意が必要です。
病院によっては退職一時金制度と企業年金制度を併用しているところもあり、退職時に一部の退職金を受け取り、残りは年金として支払われます。
資産運用ができる前払い制度
前払い制度とは、あらかじめ決められた金額が給与や賞与に上乗せして支払われる制度で、近年導入されました。
在職中に支払われるので、退職時には退職金は受け取れません。
他の病院と比較して給与や賞与が高い場合は、前払い制度が導入されているかもしれません。
前払い制度のメリットは、在職中に支給されるので老後までに資産運用ができる点です。
一方で、在職中の税金や社会保険料が高くなる可能性があるのがデメリットです。
看護師の退職金はいつ・いくらもらえるのか

看護師の退職金は勤務年数によってもらえる金額が異なります。
今回は3年目・5年目・10年目・定年まで働いた場合に退職金がいくらもらえるのか相場を紹介します。
3年目の退職金は30万円前後
勤務3年目で退職した場合にもらえる退職金の相場は、給与1ヶ月分に相当する30万円前後です。
3年目は仕事にやっと慣れてきたころなので、職場への貢献度はあまり高くなく、役職についていることも考えにくいからです。
3年目未満で退職した場合は、退職金がもらえないのが一般的です。
5年目の退職金は30~50万円
勤務5年目に退職した場合にもらえる退職金の相場は、30~50万円です。
5年目になると、自分の仕事をこなすだけではなく後輩への指導を行うこともあり、職場への貢献度も多少評価されるころでしょう。
3年目で退職した場合との大きな違いは、退職一時金制度を導入している病院であれば、ほぼ確実に退職金がもらえる点です。
5年以上勤務すると退職金の金額が大きく上がるので、可能であれば5年勤務を目指すとよいでしょう。
10年目の退職金は250~300万円
勤務10年目に退職した場合にもらえる退職金の相場は、250~300万円ほどです。
10年目になると人によっては役職についている可能性もあり、10年間継続して働いていることも併せて職場への貢献度は高くなります。
また、新卒で入社して10年目だと30代前半なので、結婚や出産などによって今後の働き方を考え直す時期でもあります。
まとまったお金が退職金として入れば、落ち着いて次の働き方を考えることができるでしょう。
20年目の退職金は450~600万円
勤務20年目に退職した場合にもらえる退職金相場は、450~600万円ほどです。
20年目になると役職についている人も多く、ベテラン社員になるので職場への貢献度もかなり高く評価されます。
しかし、病院の退職金制度によっては貢献度や役職が考慮されない可能性もあり、その場合は退職金が300万円ほどしかもらえないこともあります。
中途採用で入社したのであれば、20年目のタイミングで定年退職を迎える人もいるでしょう。
定年退職するタイミングで入るお金は老後の人生を考える際にも重要なので、評価制度がしっかりとしている病院を選ぶことをおすすめします。
勤務先別の退職金

看護師の退職金は勤務先によっても、もらえる金額が異なります。
国立病院・公立病院・私立病院それぞれの退職金事情について紹介します。
国立病院(国立病院機構)
国立病院に勤務していた看護師が定年退職した場合にもらえる退職金は、1,800万円前後です。
役職についていれば2,200~2,400万円ほどもらえることもあります。
国立病院の看護師の退職金は、他の病院に比べて退職金は高い傾向にあります。
理由は、以前は国立病院で勤務する看護師は準公務員だったためです。
準公務員の退職金は「公務員退職手当法」に基づいて支給されていますが、2015年4月に独立行政法人化したことにより、現在は準公務員ではありません。
しかし、退職金の判断水準は、準公務員時代のまま高く保たれているのが現状です。
公立病院
公立病院で勤務していた看護師が定年退職する際にもらえる退職金は、1,400~1,900万円です。
具体的には、都道府県立病院が1400万円ほど、市町村病院が1800万円ほど、政令指定都市病院は1900万円ほどです。
公立病院に勤務する看護師は地方公務員になるので、「地方公務員法」に従って退職金が支払われます。
少しでも退職金が高い病院を探しているのであれば、政令指定都市の病院に勤務するのがおすすめです。
私立病院
私立病院で勤務していた看護師が定年退職する際にもらえる退職金は、1,000~2,000万円とかなり幅があります。
私立病院の場合は、病院によって施設の規模や経営状況が異なるので、金額に差が出てしまいます。
大きな病院であっても赤字経営の場合は退職金が少ないかもしれません。
小さな病院でも経営状況が良ければ、2,000万円ほどの退職金がもらえる可能性があるでしょう。
病院の規模で判断するのではなく、退職金制度や経営状況などを確認した上で病院を選ぶことをおすすめします。
看護師の退職金計算方法と具体例

看護師の退職金計算方法について解説します。
併せて日赤・済生会の退職金についても紹介するので参考にしてみてください。
退職金計算方法
看護師の退職金計算方法は主に下記の4つのパターンがあります。
- 基本給ベース
- 固定金ベース
- 勤続年数ベース
- 功績倍数ベース
それぞれの場合の退職金計算方法を具体的に解説します。
基本給ベース
基本給ベースは、退職金の計算方法の中でも最も一般的なもので、下記の計算式で算出します。
退職金=基本給×勤続年数
例えば10年勤務して基本給が20万円だった場合の退職金は、200万円です。
基本給での計算なので残業代や交通費などは入らないので注意しましょう。
固定金ベース
固定金ベースとは、病院が設定している固定金をもとに退職金を算出する方法です。
退職金=固定金×勤続年数
例えば固定金15万円の病院に15年勤務した場合にもらえる退職金は225万円です。
固定金の相場は15万円ほどですが、病院によって異なるので10万円ほどの場合もあります。
勤続年数に基づいて退職金がわかりやすいのがメリットですが、貢献度や役職などが反映されないデメリットもあります。
勤続年数ベース
勤続年数ベースとは、病院が勤続年数ごとにもらえる退職金を定めていることです。
例えば勤続年数5年以上で100万円、10年以上で200万円といったように決められています。
就業規則に退職金について記載されているので、自分の勤続年数と照らし合わせて退職金が確認できるのがメリットです。
功績倍数ベース
功績倍数ベースとは、基本給と勤続年数に功績倍数をかけて計算する方法です。
功績倍数とは、職場への貢献度を数字に表したもので、1を基準に評価されて決まります。
具体的な計算方法は下記です。
退職金=基本給×勤続年数×功績倍数
例えば基本給20万円・勤続年数10年で、職場への貢献度が高く評価されて功績倍数が1,4だった場合の退職金は、280万円です。
反対に職場への貢献度が低いと評価されて功績倍数が0,8だった場合の退職金は、160万円です。
このように職場への貢献度によって同じ基本給・勤続年数でも、もれる退職金に差が出るのが特徴です。
自分の努力を認めてもらえるメリットもありますが、評価基準が明確ではないと不満が出るデメリットもあります。
日赤(日本赤十字病院)の退職金事情
日赤の退職金は「日本赤十字社職員退職一時給与金等支給規程」によって定められています。
退職金の計算方法は、(基本給+役職手当)×勤続年数で計算され、勤続1年以上で支払われるのが特徴です。
また、勤続25年以上になると支給率が一律になります。
具体的な例としては、勤続1年で基本給+役職手当1ヶ月分、勤続10年で基本給+役職手当11ヶ月分、勤続25年で基本給+役職手当50ヶ月分です。
済生会の退職金事情
済生会の退職金は、勤続年数3年以上で支払われるのが特徴です。
具体的な計算方法は確認できませんでしたが、過去の支給実績がわかったので紹介します。
済生会の募集要項を確認すると、勤続10年で400万円、勤続20年で1,200万円、勤続30年で3,000万円でした。
看護師の退職金でよくある疑問に回答
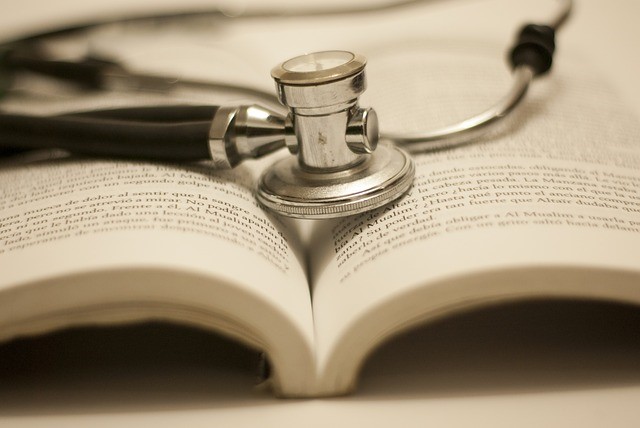
看護師の退職金について注意すべきことを紹介します。
看護師の退職金は少ない?
厚生労働省が平成30年に調査した退職金支給額によると、35年以上勤務した場合の支給額は2,173万円でした。
役職についていない一般職の看護師の退職金相場が、1,400万~1,800万円なので決して高いとは言えないです。
しかし看護師の退職金は勤務する病院や資格・役職によって大きく異なるので、一概に看護師の退職金が低いわけではありません。
看護師として転職する場合は、退職金制度についてしっかりと確認しておくことをおすすめします。
何年勤務すれば退職金がもらえる?
5年以上勤務すれば退職金がもらえることがほとんどです。
病院によっては3年勤務すれば退職金が支払われることもあります。
しかし、3年以内に退職してしまうと退職金がもらえる可能性は低いでしょう。
退職金をもらいたいのであれば最低でも3年、可能であれば5年勤務することをおすすめします。
退職金がもらえない場合がある
小さい個人病院やクリニックなどでは、退職金制度を導入していない可能性があり、退職金がもらえないかもしれません。
退職金制度は雇用主の義務ではないので退職金がなくても問題なく、特にクリニックや個人病院では退職金にまで資金が当てられないこともあるからです。
個人病院やクリニックに転職しようと考えている方は、必ず退職金制度があるか確認しておきましょう。
退職金に税金はかかる?
退職金には「所得税」と「住民税」がかかります。
そのため満額手元に残るわけではないので注意しておきましょう。
一時金として受け取るか年金として受け取るかによって計算方法や、税金の優遇措置が異なります。
一般的には同じ額の退職金の場合、一時金で受け取る方が税金の優遇措置が受けられるので最終的に手元に残る金額は多いです。
しかし、一時金で受け取ると一気に使ってしまう可能性もあるので、どちらか選べる場合は自分のライフスタイルに併せて選ぶと良いでしょう。
まとめ
この記事では看護師の退職金について、相場や計算方法を紹介しました。
看護師の退職金や転職する病院や、導入している退職金制度によって、金額やもらえるタイミングが異なります。
特に定年まで働く場合は、老後の生活を考えるととても重要になるのが退職金です。
募集要項や公式サイトを確認して、退職金制度について理解してから応募しましょう。


